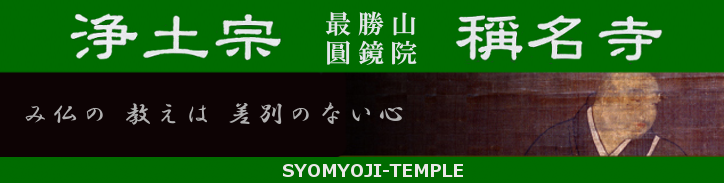稱名寺 沿革
沿 革

稱名寺は、山号を『最勝山』、院号を『圓鏡院』といいます。
浄土宗名越派 袋中上人(天文11年[1552]1月29日~寛永16年[1639]1月21日)が琉球から帰国後、丹波の地に教化遊錫の時、現在の亀岡市篠町山本に、廃寺となった天台宗寺院に草庵を建て、浄土念仏の教えを広められたのが『稱名寺』の起源といわれています。現在もその地の田圃には、稱名寺跡といわれる所があります。
その後、寛永20年(1643)8月、團忠上人により開基され、大本山 百萬遍 知恩寺の末寺として現在の地に移転されてきたと伝えられています。
かつては、中本寺の格式をもち、6ヶ寺の下寺があり、歴代の住職は紫衣を被着できる勅許をいただく寺院でありました。
しかし、悲しいことに開基から43年後の貞享3年(1686)12月4日、亀山城全滅の大火災(本町より出火し、その火は三宅町まで及んだといわれています)によって大きな被害を受け、稱名寺の堂宇や重要な記録が焼失してしまいました。
稱名寺の末寺
① 常福寺(篠町山本)
末寺の中で唯一の現存する浄土宗寺院
② 東榮寺(篠町山本)
廃寺
③ 安養寺(篠町山本)
廃寺
④ 淨行院(篠町馬堀広道)
明治時代に買収され、
現在は亀岡市立安祥小学校となっています
⑤ 松雲庵(上矢田町)
鍬山神社の北側に位置し、
現在は何も残っていません
⑥ 心行寺(古世竪町)
廃寺