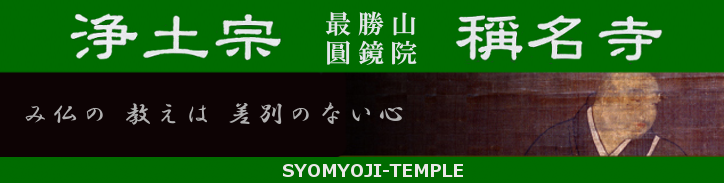和泉式部之墓
伝 和泉式部之墓
恋愛成就
芸道上達

稱名寺境内庭園の北側に和泉式部の墓と伝えられる寶篋印塔(ほうきょういんとう)があります。
全長150cm、塔身(縦27cm × 横28cm)には金剛界四仏の種子が刻まれ、笠が五層になった珍しい形の細身の塔で、相輪の部分も別のものが載せてあり、以前はもっと大形で擬寶珠のようなものが置いてあったと云われています。制作年代は不明であるが、笠の部分は室町様式の寶篋印塔五基分を重ねたものと云われています。
北村竜象編『丹波誌』4巻(大正14年)
「和泉式部の卵塔(通常は台座の上に卵形の塔身を載せた墓石、主に禅僧墓のことであるが、この地方では寺内の墓地に建てた、いわゆる詣り墓をいう)は東別院村小泉の清泉寺より移したるものと云う」
矢部朴斎著『桑下漫録』(天保15年1844)の
『俳諧盥魚』に
「和泉式部墓古世町稱名寺に有、小泉村清泉寺に有し石塔を此処へ移し也。いつの比の移たりと云年不詳つまびらかにならず、如何成故いかがなるゆえと云事もしらず、只里人の口号而己こうごうにておのれ不審也と云々
今按いまあんずるに本堂の前北の方に高4尺斗にして、下に方石此四方に梵字を彫、上に丸き石、其上に三重に刻みし卵塔有、可是成これなるべく、巳すでに前さへ難分由わかりがたきよしに云ば、今尚不分明いまなおぶんめいせず、尤もっとも在清泉寺小式部墓と云ると同じ様也」
現在、同寺にあるものと異なる形の石塔のように表現している。
稱名寺は寛永20年(1643)8月に鵜ノ川右岸下流域の山本村からこの地に移転し、貞享3年(1686)12月4日、火災にあった。
「和泉式部」・・・水を連想させる名前(和泉)
また古くから近くには湧き水があり
(現 親水公園)
水に関連したものを多く揃えることで、二度とあのような
大火に見舞われないように祈念したのではないかと言われています。
このことから、宝篋印塔は江戸時代になってからここに建てられたことになる。
以前に台座があったところへ上部を持ってきたとも考えられる。
和泉式部略歴
大江雅致の娘。
和泉守の橘道貞の妻となり、父の官名と夫の任国とを合わせて「和泉式部」と呼ばれた。
この道貞との間に娘小式部内侍を儲ける。夫とは後に離れるが、娘は母譲りの歌才を示している。
まだ道貞の妻だった頃、冷泉天皇の第三皇子である為尊親王との熱愛が世に喧伝される。為尊親王の死後の翌年、今度はその同母弟である「帥宮(そちのみや)」と呼ばれた敦道親王の求愛を受ける。この求愛は熱烈を極め、親王は式部を邸に迎えようとし、結果として正妃が家出するに至った。
敦道親王との間に一子永覚を儲けるが、兄と同じく、敦道親王も寛弘四年(1007)に早世する。服喪を終えた式部は、寛弘末年(1008-1011)頃から一条天皇の中宮藤原彰子に女房として出仕を始めた。この頃、同じく彰子の周辺にいた紫式部・伊勢大輔・赤染衛門らとともに宮廷サロンを築くことになる。四十歳を過ぎた頃、彰子の父道長の家司藤原保昌と再婚し、丹後守となった夫とともにその任国に下った。万寿二年(1025)、式部に先立ち娘の小式部内侍が死去。式部晩年の詳細は知られていない。
歌人式部の真情に溢れる作風は、恋歌・哀傷歌・釈教歌にもっともよく表され、殊に恋歌に情熱的な秀歌が多いのは数々の恋愛遍歴によるものであろう。その才能は、同時代の大歌人藤原公任にも賞賛され、正に男女を問わず一、二を争う王朝歌人といえる。伝存する家集は、『和泉式部正集』『和泉式部続集』や、秀歌を選りすぐった『宸翰本和泉式部集』など。また『拾遺集』以下、勅撰集に二百四十六首の和歌を採られ、死後初の勅撰集『後拾遺集』では最多入集歌人の名誉を得た。
さらに、敦道親王との恋の顛末を記した物語風の日記『和泉式部日記』(寛弘4年(1007)頃成立)は、わが国の女流文学を代表する一つとしてよく知られている。本作品の特長は、恋愛に関する式部のありのままの心情描写が、取り交わされた多くの和歌を交えてあらわされていることである。