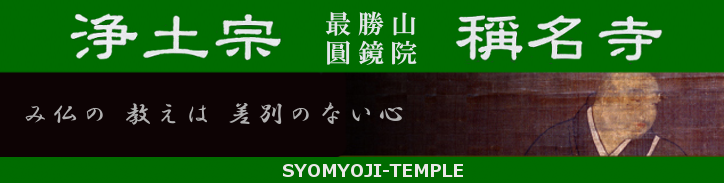法然上人の生涯

元祖法然上人像(稱名寺蔵)
生い立ちと出家・授戒
長承2年(1133)4月7日、美作国久米南条久米稲岡庄(現在の岡山県久米郡久米南町)の押領使 漆間時国(うるまのときくに)と、母・秦氏(はたうじ)との子として生まれる。生誕地は、誕生寺(出家した熊谷直実が建立したとされる)になっている。
保延7年(1141)9歳のとき、土地争論に関連し、預所(荘園を領主から預かって管理する人)の源内武者定明(げんないむしゃさだあきら)が父に夜討をしかけて殺害してしまうが、
父時国は臨終の枕辺に居並ぶ家族に向かって
「われこのきずいたむ。人またいたまざらんや。われこのいのちを惜しむ。人あに惜しまざらんや。」と、
自他一体感に基づいて、強く仇討ちを戒められたのでした。
この遺言は仇討ちを当然視する武士の風習、とりわけ曾我兄弟の登場する時代とほど遠くない時代、50年前ほど以前のことでしたが、それとはまったく逆の方向を示すものでした。
仇討ちを断念し、菩提寺(岡山県勝田郡奈義町高円)の院主であった、母方の叔父の観覚(かんがく)のもとに引き取られた。その才に気づいた観覚は、出家のための学問をさずけ、また、当時の仏教の最高学府であった比叡山での勉学を勧めた。
天養2年(1145)13歳(異説には久安3年 15歳)で比叡山延暦寺に登り、西塔北谷の持宝房源光に師事した。源光は自分ではこれ以上教えることがないとして、久安3年(1147)戒壇院で戒を授かって文字通り出家者となりました。その後、同じく比叡山の功徳院阿闍梨皇円の下で「天台三大部」(『法華玄義』『法華文句』『摩訶止観』各10巻)の勉学にいそしみました。
久安6年(1150)皇円のもとを辞し、比叡山西塔黒谷に移り慈眼房叡空(えいくう)に師事することになりました。「年少であるのに出離の志をおこすとはまさに法然道理の聖(ひじり)である」と叡空から絶賛され、このとき、18歳で法然房という房号を、源光と叡空から一字ずつとって源空という諱(いみな)を授かり、法然房源空となった。法然は「智慧第一の法然房」と称され、保元元年(1156)24歳のとき比叡山をくだって、清涼寺(京都市右京区)や醍醐寺(京都市伏見区)などに遊学した。
浄土宗の開宗

善導大師像(稱名寺蔵)
承安5年(1175)43歳の時、善導大師の『観無量寿経疏』(『観経疏』)によって回心を体験し、専修念仏を奉ずる立場に進んで浄土宗をひらき、比叡山を下りて東山吉水に住んで、念仏の教えを広めた。この1175年が浄土宗の立教開宗の年とされる。かれのもとには延暦寺の官僧であった証空、隆寛、親鸞らが入門するなどしだいに勢力をひろげた。
養和元年(1181年)、前年に焼失した東大寺の大勧進職に推挙されるが辞退し、俊乗房重源を推挙した。
文治2年(1186)、大原勝林院で聖浄二門を論じた。これを「大原問答」と呼んでいる。
建久元年(1190年)、重源の依頼により再建中の東大寺の大仏殿に於いて浄土三部経を講ずる。
建久9年(1198)、専修念仏の徒となった九条兼実の懇請を受けて『選択本願念仏集』を著した。
元久元年(1204)、後白河法皇13回忌法要である「浄土如法経(にょほうきょう)法要」を法皇ゆかりの寺院「長講堂」(現、京都市下京区富小路通六条上ル)で営んだ。絵巻「法然上人行状絵図(国宝)」にその法要の場面が描かれている。
元久元年、比叡山の僧徒は専修念仏の停止を迫って蜂起したので、法然は「七箇条制誡」を草して門弟190名の署名を添え延暦寺に送った。しかし、元久2年(1205年)の興福寺奏状の提出が原因のひとつとなって建永2年(1207)後白河上皇により念仏停止の断が下された。
念仏停止の断のより直接のきっかけは、奏状の出された年に起こった後鳥羽上皇の熊野詣の留守中に院の女官たちが法然門下で唱導を能くする遵西・住蓮のひらいた東山鹿ヶ谷草庵(京都市左京区)での念仏法会に参加し、さらに出家して尼僧となったという事件であった。この事件に関連して、女房たちは遵西・住蓮と密通したという噂が流れ、それが上皇の大きな怒りを買ったのである。
讃岐配流と晩年
建永2年は改元して承元元年となったが、この年、法然は還俗させら「藤井元彦」を名前として、土佐国(実際には讃岐国)に流罪となった。なお、親鸞はこのとき越後国に配流とされた。
讃岐国滞在は10ヶ月と短いものであったが、九条家領地の塩飽諸島本島や西念寺(現香川県仲多度郡まんのう町)を拠点に、75歳の高齢にもかかわらず讃岐じゅうに布教の足跡を残し、空海の建てた由緒ある善通寺にも参詣している。法然を偲ぶ法然寺(京都の法然寺とは別。讃岐に後の時代に建てられた)も高松市に所在する。
承元元年(1207)12月に赦免されて讃岐を離れ、讃岐国流罪から戻った法然が摂津国豊島郡(現箕面市)の勝尾寺に滞在、承元4年(1210)3月21日まで滞在していた記録が残っている。翌年の建暦元年(1211)には京に入り、吉水にもどった。
建暦2年(1212)1月25日、京都東山大谷(京都市東山区)で死去した。享年80。
なお、死の直前の建暦2年1月23日には弟子の源智の願いに応じて、遺言書「一枚起請文」を記している。